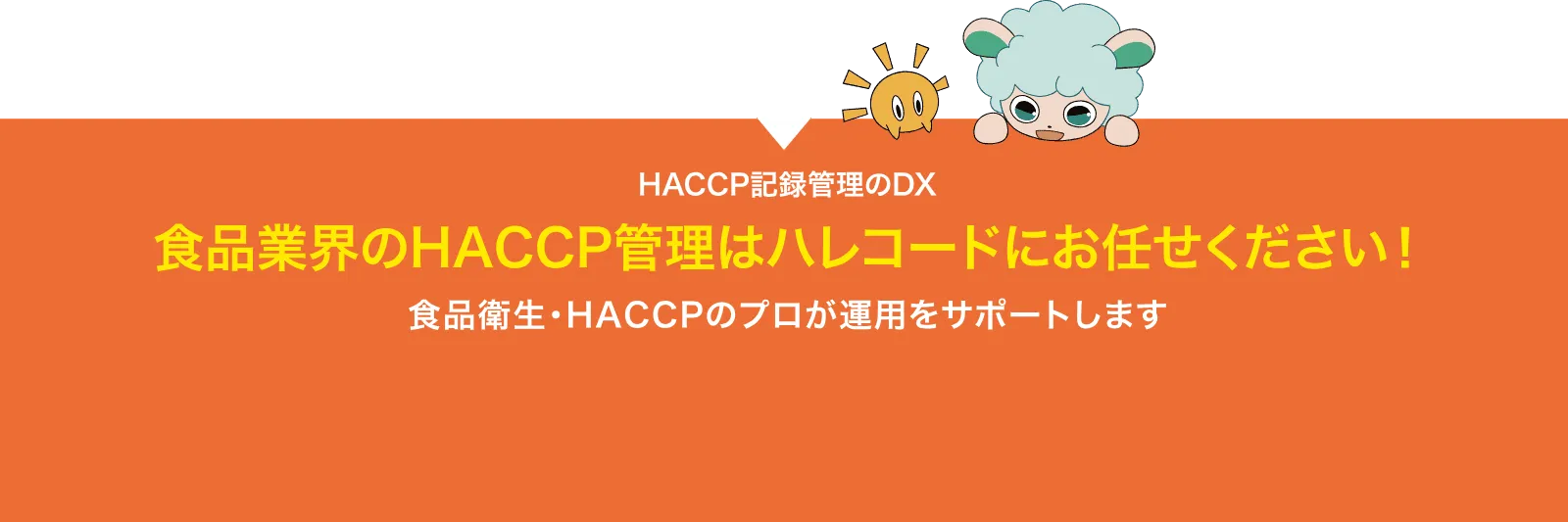HACCP(ハサップ)とは?食品衛生法での義務化で変わる対応方法を詳しく解説
食品の安全性確保において、HACCP(ハサップ)は世界標準の衛生管理手法として定着しています。2021年6月から食品衛生法の改正により、原則としてすべての食品事業者にHACCP導入が義務化されました。この変化は多くの事業者にとって対応が必要な重要課題です。本記事では、HACCPの基本概念から食品衛生法での義務化の詳細、そして実際の導入手順まで、食品事業者が知っておくべき情報を徹底解説します。コスト面での懸念を持つ小規模事業者の方にも参考になる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」についても詳しくご説明しますので、これからHACCP対応を検討している方は、ぜひご参照ください。
HACCP(ハサップ)の基本概念と歴史
HACCP(ハサップ)は、食品の安全性を確保するための科学的な衛生管理システムです。
HACCPの定義と概要
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)は、「危害要因分析重要管理点」と訳され、食品の安全性を確保するための体系的な衛生管理手法です。原材料の受入から製造・出荷までの全工程において、微生物による汚染や金属の混入などの危害要因を分析し、特に重要な工程(重要管理点:CCP)を継続的に監視・記録する方法です。 製造工程全体を管理することで、問題発生の未然防止と迅速な対応を可能にする のがHACCPの最大の特徴です。
HACCPの誕生と世界的な広がり
HACCPは1960年代、アメリカの宇宙開発計画において宇宙食の安全性確保のために開発されました。NASAとピルズベリー社が共同で、宇宙飛行士が食中毒にならないよう100%安全な宇宙食を開発する過程で確立された手法です。その後、1993年にはコーデックス委員会によってHACCPガイドラインが策定され、国際的な食品衛生管理の標準として世界中に広がりました。
現在では欧米を中心に多くの国でHACCPの導入が義務化されており、国際的な食品取引においても重要な基準となっています。日本も国際標準に合わせる形で、2021年に食品衛生法の改正によりHACCPに沿った衛生管理を義務化しました。
従来の食品衛生管理とHACCPの違い
HACCPが従来の衛生管理と大きく異なるのは、その管理手法と効果の点です。
従来の抜き取り検査方式の限界
従来の食品衛生管理は、主に「抜き取り検査」による方法が中心でした。これは最終製品の一部をサンプリングして検査する方法で、不良品が見つかった場合にのみ対応する事後対応型の管理でした。しかし、この方法には限界があります。全ての製品の安全性を保証できず、検査時には既に多くの製品が出荷されている可能性があります。また、問題が見つかった時点で大量の製品ロスが発生し、原因の特定が難しく同じ問題が繰り返される可能性もあります。
抜き取り検査では全製品の安全性を担保できず、問題発見が遅れることで大きな被害に発展するリスク があります。
HACCPによる予防型管理の特徴
一方、HACCPは「予防型」の衛生管理システムです。製造工程全体を継続的に監視し、重要な工程(CCP)で問題を早期発見できます。問題発生時に即時対応が可能で、記録が残るためトレーサビリティが確保されます。また、科学的根拠に基づいた管理により、効率的な衛生管理が可能になります。
HACCPでは、各工程での管理状況を常に記録するため、問題が発生した場合でも原因究明が容易になります。また、危害要因を事前に分析して対策を講じることで、食品事故を未然に防ぐことができます。
| 比較項目 | 従来の抜き取り検査 | HACCP管理 |
|---|---|---|
| 管理タイプ | 事後対応型 | 予防型 |
| 検査対象 | 最終製品の一部 | 全工程・全製品 |
| 問題発見 | 出荷後の場合も多い | 製造中にリアルタイム検出 |
| 対応速度 | 遅い | 迅速 |
| 製品ロス | 大きい | 最小限に抑えられる |
| 記録・証拠 | 限定的 | 体系的に保存 |
食品衛生法改正とHACCP義務化の背景
2021年6月から始まったHACCP義務化には、国内外の様々な背景があります。
国際的な食品安全基準との整合性
食品衛生法改正の大きな背景の一つは、国際的な食品安全基準との整合性を図る必要性です。欧米やアジアの主要国では既にHACCP導入が義務化されており、国際的な食品取引においてもHACCPベースの衛生管理が前提となっています。日本の食品産業の国際競争力を維持・向上させるためにも、 国際標準に合わせた衛生管理体制の構築が不可欠 でした。
特に輸出促進を国の重要戦略とする中で、海外の基準に対応した食品安全システムの導入は急務となっていました。また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた食の安全確保という側面もありました。
食品事故防止と消費者信頼の向上
国内では食中毒や異物混入などの食品事故が依然として発生しており、より効果的な予防対策の導入が求められていました。HACCPの科学的・体系的アプローチは、こうした食品事故の未然防止に効果的です。
また、消費者の食の安全・安心への意識が高まる中で、食品事業者の衛生管理の取り組みを見える化し、消費者からの信頼を獲得することも重要な目的でした。HACCPに基づく衛生管理は、その科学的根拠と記録管理により、消費者に対して食品の安全性を客観的に示すことができます。
食品衛生法改正の概要
2018年6月に公布された改正食品衛生法では、重要な変更点がありました。原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられ、事業者の規模や業種に応じた2つの管理区分(「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」)が設定されました。また、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設、食品リコール情報の報告制度の創設、食品用器具・容器包装へのポジティブリスト制度導入も行われました。
これらの改正は、公布から2年の準備期間を経て、2021年6月1日から完全施行されました。HACCPに沿った衛生管理の義務化により、日本の食品安全管理体制は国際水準に引き上げられることになりました。
HACCP義務化の対象事業者と適用区分
HACCP義務化は、事業者の規模や業種によって適用される基準が異なります。
「HACCPに基づく衛生管理」が求められる事業者
大規模事業者や特定の業種については、より厳格な「HACCPに基づく衛生管理」(コーデックスHACCP7原則を要件とする本格的なHACCP)の実施が求められます。対象となるのは主に大規模事業者(食品製造業者で一般的に従業員数50人以上)、と畜場・食鳥処理場、乳・乳製品・食肉製品・水産加工品などの高度な衛生管理を要する食品の製造加工業者、広域流通食品の製造事業者です。
これらの事業者は国際的なHACCP基準に準拠した完全なHACCP管理システムを構築・運用する必要があります 。計画的なチーム編成、危害要因分析、重要管理点の設定、検証など、7原則12手順に則った管理体制の確立が求められます。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象
小規模事業者や一般飲食店などについては、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という簡略化された方法での対応が認められています。対象となるのは小規模事業者(食品製造業者で一般的に従業員数50人未満)、飲食店・喫茶店・菓子店などの小売業、給食施設・弁当屋・仕出し屋、旅館・ホテルなどです。
これらの事業者は、各業界団体が作成し厚生労働省が確認した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を参考にして衛生管理を行うことができます。手引書には業種ごとの一般的な衛生管理のポイントや、簡略化されたHACCP管理の方法が示されています。
HACCP義務化の対象外となる事業者
以下の事業者は、HACCPに沿った衛生管理の対象外とされています。食品の採取業(農業、漁業など)、収穫後の生産・採取段階の一次産品を取り扱う事業者(洗浄、選別、乾燥など)、自動販売機(内部で調理などを行わないもの)、または提供する食事の数が一回20食程度未満の営業者(例:学校、病院、事業所、保育所、老人ホームなどの給食施設)、食品を製造・加工せず、かつ小分け包装も行わない事業者などが該当します。
ただし、これらの事業者であっても、自主的に衛生管理の向上に取り組むことが推奨されています。また、対象外であっても一般的な衛生管理(手洗いや清掃など)は引き続き必要です。
| 区分 | 対象事業者 | 求められる対応 |
|---|---|---|
| HACCPに基づく衛生管理 | 大規模事業者、と畜場など | コーデックスHACCP7原則に基づく完全実施 |
| HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | 小規模事業者、飲食店など | 業界団体の手引書に基づく簡略化された管理 |
| HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | 小規模事業者、飲食店など | 業界団体の手引書に基づく簡略化された管理 |
| 対象外 | 農業、漁業、一部給食施設など | 一般衛生管理の実施 |
HACCP導入の7原則12手順とは
HACCP導入は国際的に標準化された「7原則12手順」に従って進めることが基本です。
HACCP導入の準備段階(手順1〜5)
HACCPを効果的に導入するためには、まず準備段階として5つの手順を踏むことが重要です。HACCPチームの編成では、様々な専門知識を持つメンバーで構成されるチームを作ります。製造、品質管理、設備管理など、複数の部門からメンバーを選出することが必要です。製品説明書の作成では、製品の特性(原材料、加工方法、包装形態、保存方法、消費期限など)を文書化します。特にアレルゲンや微生物制御に関する情報は重要です。
意図する用途・対象者の確認では、製品がどのように使用されるか、誰が消費するのかを明確にします。特に、乳幼児や高齢者、アレルギーを持つ方など特定の消費者への注意点を明らかにします。製造工程図の作成では、原材料の受入から製品の出荷までの全工程を図式化します。各工程での温度・時間などの条件も記載します。最後に製造工程図の現場確認を行い、作成した工程図が実際の製造現場と一致しているかを確認します。 現場の実態を正確に反映した工程図を作成することがHACCP成功の鍵 です。
危害要因分析と重要管理点の設定(手順6〜7)
準備段階の次に、HACCP導入の核心部分である危害要因分析と重要管理点の設定を行います。危害要因分析(HA)の実施(原則1)では、各工程で発生する可能性のある危害要因(生物的・化学的・物理的危害)を洗い出し、その重要度と発生頻度を評価します。そして、それぞれの危害要因に対する管理手段を決定します。
重要管理点(CCP)の決定(原則2)では、危害要因を確実に管理できる工程を重要管理点として特定します。一般的にはディシジョンツリー(決定木)と呼ばれる判断基準を用いて決定します。例えば、加熱殺菌工程や金属検出工程などが典型的なCCPとなります。
管理基準の設定と監視方法(手順8〜10)
重要管理点が決まったら、具体的な管理方法を設定します。管理基準(CL)の設定(原則3)では、各CCPにおいて、安全性を確保するための具体的な管理基準を設定します。例えば、「中心温度75℃で1分以上の加熱」「X線検出器の感度○○mm以上」などの数値基準です。
モニタリング方法の設定(原則4)では、管理基準が守られているかを継続的に監視する方法を定めます。「誰が」「何を」「どのように」「どのくらいの頻度で」モニタリングするかを明確にします。改善措置の設定(原則5)では、モニタリングの結果、管理基準から逸脱した場合の対応方法を事前に決めておきます。不適合品の処理方法や、工程を正常に戻すための手順などを含みます。
検証と記録(手順11〜12)
最後に、HACCPシステムが適切に機能しているかを確認し、記録する仕組みを整えます。検証方法の設定(原則6)では、HACCPプランが適切に機能しているかを確認するための方法を設定します。これにはモニタリング機器の校正、記録の確認、微生物検査などによる検証、内部監査やシステムの定期的な見直しなどが含まれます。
記録と保存方法の設定(原則7)では、HACCPプランの内容と実施状況を文書化し、記録を保存する方法を決定します。 記録は食品の安全性を証明する重要な証拠 となるため、適切な保管期間と方法を定めることが重要です。
これらの12手順に沿って計画的にHACCPを導入することで、効果的な食品安全管理システムを構築することができます。特に小規模事業者の場合は、業界団体の手引書を参考にしながら、自社の状況に合わせて必要な手順を実施していくことが推奨されています。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実践方法
小規模事業者や飲食店は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という簡略化された方法でHACCPに対応できます。
業界団体作成の手引書の活用方法
小規模事業者や一般飲食店などは、各業界団体が作成した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を活用することが最も効率的な対応方法です。これらの手引書は厚生労働省のウェブサイトで公開されており、無料でダウンロードできます。
手引書の活用では、まず自社の業種に合った手引書を選びます。飲食店、菓子製造業、弁当・惣菜製造業など、様々な業種別の手引書が用意されています。次に手引書の内容を理解し、一般衛生管理のポイントや重要管理のポイントなど、手引書の基本的な内容を把握します。手引書の内容をそのまま適用するのではなく、自社の製品や工程に合わせて必要な部分を選択・調整することが重要です。多くの手引書には記録用の様式例が掲載されているため、これらを活用して日々の記録を取りましょう。
手引書は単なる参考資料ではなく、実際に活用することで法的要件を満たすための重要なツール です。ただし、形だけ真似るのではなく、自社の実情に合わせた運用が重要です。
簡易版HACCPの実施手順
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、本格的なHACCPよりも簡略化された手順で実施できます。まず一般衛生管理の徹底から始めます。手洗い、清掃・消毒、温度管理、従業員の健康管理など、基本的な衛生管理を確実に行います。
次にメニュー・製品ごとの危害要因の確認を行い、提供する食品に関連する主な危害要因(アレルゲン、細菌汚染など)を把握します。重要な管理ポイントの特定では、手引書を参考に、特に注意が必要な工程(加熱調理、冷却、交差汚染防止など)を特定します。管理方法の決定と実施では、各管理ポイントでの具体的な管理方法(温度、時間など)を決め、実行します。記録の作成では、日々の管理状況を簡潔に記録します。チェックリスト形式など、記入が容易な方法を選びましょう。最後に定期的な見直しを行い、問題が発生した場合や、メニュー・製品の変更時には管理方法を見直します。
小規模事業者向けの記録方法と様式例
記録は「証拠」として非常に重要ですが、小規模事業者にとって記録作業の負担は大きな課題です。効率的な記録方法として、チェックリスト形式の活用があります。チェック項目を予め印刷しておき、確認したらチェックを入れるだけの簡易な様式です。既存の記録との統合では、既に行っている日報や作業記録にHACCP関連の項目を追加します。写真による記録では、温度計の表示などを写真に撮り、日付と時間が記録される方法を使います。DXツールの活用では、タブレットやスマートフォンのアプリを使った記録方法(各種HACCP記録アプリが開発されています)を利用できます。
記録様式の例として、衛生管理日誌(従業員の健康状態、施設・設備の衛生状態など)、温度管理記録表(冷蔵庫・冷凍庫、調理温度など)、加熱調理記録(中心温度、加熱時間など)、原材料受入記録(納品日、温度、品質状態など)、清掃・消毒記録などが基本となります。
これらの記録は最低でも1年間の保管が推奨されています。記録は保健所の立入検査時に確認される重要な資料となります。
一般衛生管理プログラムの重要性
HACCPは単独で機能するものではなく、一般衛生管理という土台の上に成り立つシステムです。
HACCPの前提となる一般衛生管理とは
一般衛生管理プログラム(Prerequisite Programs: PRP)とは、食品の安全を確保するための基本的な衛生管理のことで、HACCPを効果的に機能させるための前提条件です。国際的には「前提条件プログラム」や「GHP(適正衛生規範)」とも呼ばれています。
HACCPが効果を発揮するためには、まず一般衛生管理が適切に実施されていることが絶対条件 です。いくら精緻なHACCPプランを策定しても、基本的な衛生管理ができていなければ、食品の安全は確保できません。
一般衛生管理には施設・設備の衛生管理(構造、レイアウト、清掃、保守など)、従業員の衛生管理(手洗い、健康管理、作業着の清潔さなど)、原材料の受入管理(仕入先の評価、受入検査など)、温度・時間管理(保管温度、加工時間など)、交差汚染防止(作業区域の分離、器具の区別など)、廃棄物管理(ゴミの適切な処理、害虫防止など)、水質管理(使用する水の安全確保)、教育・訓練(従業員への衛生教育)などの項目が含まれます。
一般衛生管理の具体的な実施方法
一般衛生管理を効果的に実施するためには、重要なポイントに注意することが必要です。責任者の明確化では、各衛生管理項目の責任者を決め、責任を持って実施・確認する体制を作ります。手順書の作成では、清掃方法、手洗い手順など、基本的な衛生作業の標準手順を文書化します。チェックリストの活用では、日々の確認事項をリスト化し、確実に実施・記録できるようにします。定期的な見直しでは、実施状況を定期的に確認し、問題があれば改善します。従業員教育では、なぜ衛生管理が重要なのかを理解させ、正しい実施方法を教育します。
特に重要なのは、作業者が「なぜその衛生管理が必要か」を理解することです。理由を理解せずに形だけ実施しても、本当の意味での食品安全は確保できません。
5S活動とHACCPの連携
一般衛生管理を効率的に実施するためには、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)との連携が非常に効果的です。5Sは日本発の管理手法で、職場環境の改善と品質向上を目的としていますが、食品衛生管理にも極めて有効です。
5SとHACCPの連携において、整理(Seiri)では不要なものを取り除くことで、清掃しやすい環境を作り、害虫の隠れ場所をなくします。整頓(Seiton)では道具や資材を決められた場所に配置することで、交差汚染のリスクを減らします。清掃(Seiso)では定期的な清掃により、細菌の繁殖を防止し、異物混入のリスクを低減します。清潔(Seiketsu)では上記3Sを維持することで、常に衛生的な状態を保ちます。躾(Shitsuke)ではルールや手順を守る習慣づけにより、HACCPの持続的な実施を可能にします。
5S活動はHACCPの基盤となる一般衛生管理を支える重要な活動です。特に小規模事業者の場合、まず5Sから取り組むことで、効率的にHACCP導入の準備を進めることができます。
HACCP導入のメリットと課題
HACCP導入には様々なメリットがありますが、導入・運用の過程ではいくつかの課題も存在します。
企業にとってのHACCP導入メリット
HACCPを導入することで、食品事業者には多くのメリットがあります。食品事故の未然防止では、科学的・体系的なアプローチにより、食中毒や異物混入などの事故を予防できます。クレーム・リコールの減少では、事前対策により製品の安全性が向上し、クレームやリコールの発生が減少します。これにより、対応コストや信用失墜による損失を大幅に削減できます。
製造プロセスの効率化では、製造工程の見直しや標準化により、ムダの削減や作業効率の向上が期待できます。従業員の意識向上では、衛生管理の重要性や各工程の意味を理解することで、従業員の品質・安全に対する意識が高まります。取引上の優位性では、取引先からの信頼獲得や、新規取引先の開拓に有利になります。特に大手小売業者や外食チェーンとの取引では、HACCP対応が取引条件となることも増えています。海外展開の可能性拡大では、国際的な食品安全基準に対応することで、輸出や海外進出の機会が広がります。コンプライアンスの確保では、法的要件を満たすことで、行政処分や罰則のリスクを回避できます。
HACCP導入は単なる法令遵守のためだけでなく、企業の競争力強化や経営改善にもつながる重要な投資 と考えることができます。
導入・運用における課題と対策
一方、HACCP導入・運用には課題も存在します。知識・経験不足では、特に小規模事業者でHACCPに関する知識や経験が不足していることが多い課題です。対策として業界団体の手引書の活用、保健所や専門機関の相談窓口の利用、セミナーへの参加があります。
人材・時間の不足では、日々の業務に追われ、HACCP導入に充てる人材や時間を確保できない問題があります。対策として段階的な導入計画の策定、外部コンサルタントの活用、優先順位の明確化があります。コスト負担では、施設・設備の改修や検査機器の導入など、初期投資が必要な場合があります。対策として補助金・支援制度の活用、必要最小限の投資から始める、費用対効果の高い対策の優先実施があります。
記録作業の負担では、日々の記録作業が大きな負担となることがあります。対策としてシンプルな記録様式の採用、タブレットやアプリの活用、既存の記録との統合があります。形骸化のリスクでは、時間の経過とともに形だけの運用になってしまうリスクがあります。対策として定期的な内部監査や見直し、従業員教育の継続、成功事例の共有があります。
小規模事業者向けの導入ステップ
小規模事業者がHACCPを無理なく導入するためのステップがあります。基礎知識の習得では、まずはHACCPの基本的な考え方を理解しましょう。業界団体のセミナーや保健所の講習会などを活用してください。現状の衛生管理の見直しでは、既存の衛生管理状況を確認し、改善すべき点を洗い出します。5S活動から始めるのも効果的です。
業界の手引書の入手では、自社の業種に合った手引書を入手し、内容を理解します。厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできます。一般衛生管理の強化では、手引書を参考に、まずは一般衛生管理(手洗い、清掃・消毒、温度管理など)を徹底します。重要管理ポイントの特定と管理方法の決定では、提供する食品の特性に応じて、特に注意すべきポイントと具体的な管理方法を決めます。記録様式の作成と記録開始では、シンプルな記録様式を作成し、日々の管理状況を記録します。従業員への教育では、全従業員にHACCPの目的と各自の役割を理解してもらいます。定期的な見直しと改善では、実施状況を定期的に確認し、必要に応じて改善します。
HACCP導入は一度に完璧を目指すのではなく、できるところから段階的に進めることが重要です。「まずは始める」という姿勢で取り組み、少しずつレベルアップしていきましょう。
HACCPに役立つIT・IoT技術の活用
テクノロジーの進化により、HACCP管理を効率化・高度化するためのIT・IoTソリューションが数多く登場しています。
HACCP管理における記録のデジタル化
HACCP管理において最も大きな負担となるのが日々の記録作業です。この記録作業をデジタル化することで、大幅な業務効率化が可能になります。
記録のデジタル化には多くのメリットがあります。作業時間の削減では、手書きに比べて入力が容易で、データの集計・分析も自動化できます。記録ミスの防止では、入力値の自動チェックや必須項目の管理により、記録漏れや誤記を防止できます。データの一元管理では、複数拠点のデータを一元管理でき、本部での監視・分析が容易になります。保管スペースの削減では、紙の記録の保管場所が不要になります。データ検索の効率化では、過去の記録を瞬時に検索できるため、問題発生時の原因究明が迅速になります。
デジタル化のための主なツールとして、専用のHACCPアプリ(スマートフォンやタブレットで利用できるHACCP記録専用アプリ)、クラウド型食品衛生管理システム(複数拠点の一元管理や高度な分析機能を持つシステム)、電子チェックリスト(紙のチェックリストをデジタル化したシンプルなツール)、表計算ソフトのテンプレート(Excelなどのテンプレートをカスタマイズして利用)があります。
紙での記録から電子記録へ移行することで、作業負担の軽減と記録精度の向上を同時に実現できます 。特に複数店舗を持つチェーン店や、大規模な製造工場では効果が大きいでしょう。
温度センサーなどのIoT機器の活用
IoT(モノのインターネット)技術を活用することで、これまで人手で行っていた各種モニタリングを自動化できます。特に温度管理は食品安全の要となる部分であり、IoT化による効果が大きい領域です。
IoT活用の主な例として、自動温度記録システム(冷蔵庫・冷凍庫・調理機器などの温度を自動的に記録するシステム。クラウドで管理することで、異常値をリアルタイムで検知・通知することも可能です)、調理器具の自動制御(調理器具にセンサーを搭載し、適切な温度・時間で自動制御。加熱不足などのリスクを防止します)、ワイヤレス中心温度計(食品の中心温度をワイヤレスで測定し、データを自動記録するシステム)、入退室管理システム(ICカードやQRコードによる入退室管理。誰がいつ作業区域に入ったかを記録し、食品防御にも役立ちます)、異物検出AI(カメラとAIを組み合わせた高精度な異物検出システム。人間の目では発見しづらい微小な異物も検出可能です)があります。
これらのIoT技術は、人手不足の解消や人為的ミスの防止だけでなく、24時間365日の連続モニタリングによる安全性向上にも大きく貢献します。
中小企業でも導入しやすいITツール
大企業向けの高度なシステムは高コストですが、中小企業でも導入しやすい低コストのITツールも増えています。
クラウド型HACCPアプリでは、月額数千円から利用できるサブスクリプション型のアプリが多数登場しています。初期投資を抑えつつ、必要な機能だけを利用できます。低価格IoTセンサーでは、数千円〜数万円の手頃な価格の温度センサーなどが販売されています。Wi-Fi接続タイプなら既存のネットワークを活用できます。汎用タブレットの活用では、専用機器ではなく、一般的なタブレットとアプリを組み合わせることで、低コストでのデジタル化が可能です。スマートフォンアプリでは、従業員のスマートフォンを活用した手洗いチェックや衛生教育アプリなども登場しています。無料のテンプレートでは、行政機関や業界団体が提供する無料のExcelテンプレートを活用する方法もあります。
IT導入補助金などの支援制度を活用すれば、さらにコスト負担を軽減できます。無理なく始められる小規模なIT化から段階的に進めることをおすすめします。
ITツール導入のポイントは、「現場の負担を実際に軽減できるか」という視点で選ぶことです。高機能でも操作が複雑なシステムでは、かえって現場の負担が増える可能性があります。シンプルで使いやすいツールを選び、徐々に慣れていくことが成功の鍵です。
行政による支援制度と相談窓口
HACCP導入を支援するための様々な制度や相談窓口が用意されています。特に小規模事業者は積極的に活用しましょう。
国や自治体の支援制度
HACCPの義務化に伴い、国や地方自治体では様々な支援制度を設けています。HACCP導入の補助金・助成金として、食品製造業等HACCP対応施設整備事業(HACCPに対応するための施設や機器の整備費用を補助)、中小企業等経営強化法に基づく税制優遇措置(HACCP導入のための設備投資に対する税制優遇)、各都道府県・市町村独自の補助金制度(地域によって独自の支援制度がある場合も)があります。
IT導入補助金は、HACCP管理用のITツール導入費用を補助する制度で、デジタル化を進める中小企業向けの支援制度です。融資制度では、日本政策金融公庫の「食品関係企業向け設備資金融資」、各地域の信用保証協会による保証制度があります。専門家派遣制度では、中小企業基盤整備機構や各都道府県の産業支援センターによる専門家派遣、HACCPに詳しいコンサルタントを無料または低コストで派遣してもらえる制度があります。
これらの支援制度は期間限定のものや予算に上限があるものが多いため、早めに情報収集して申請することが重要 です。各地域の商工会議所や保健所、都道府県の担当部署に問い合わせると、最新の情報を得ることができます。
相談窓口と情報源
HACCP導入に関する相談窓口や情報源があります。各地域の保健所にはHACCP相談窓口が設置されており、無料で相談できます。現場の実情に合わせたアドバイスが受けられる貴重な窓口です。
業界団体の相談窓口では、各業界団体(例:全国菓子工業組合連合会、日本惣菜協会など)で会員向けの相談窓口を設けています。業界特有の課題について専門的なアドバイスが受けられます。中小企業支援機関では、中小企業基盤整備機構、各都道府県の産業支援センター、商工会議所などでも支援を行っています。厚生労働省のウェブサイトでは、最新の法令情報や手引書など、公式情報が掲載されています。「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化」ページが特に参考になります。食品安全マネジメント協会(JFSM)は、国内の食品安全に関する認証制度(JFS規格)を運営する団体で、有益な情報を提供しています。
HACCP講習会・セミナーの活用法
HACCP導入の知識を得るために、各種講習会やセミナーを活用することも効果的です。
多くの保健所や自治体で定期的にHACCP講習会を開催しています。基本的に無料または低額で参加でき、地域の実情に合った情報が得られます。業界団体主催のセミナーでは、業界特有の課題に焦点を当てたセミナーで、実践的な内容が多いのが特徴です。食品衛生協会の講習会では、地域の食品衛生協会でも実践的な講習会を開催しています。民間企業のセミナーでは、コンサルティング会社やシステム開発会社などが主催するセミナーも参考になります。有料の場合が多いですが、専門的で質の高い内容が期待できます。オンラインセミナー・eラーニングでは、近年はオンラインで受講できるセミナーやeラーニングも増えており、時間や場所の制約なく学べます。
講習会やセミナーを最大限活用するためのポイントとして、単に参加するだけでなく、自社の具体的な課題について質問を準備しておく、可能であれば複数の担当者で参加し、情報共有を図る、講師や他の参加者とのネットワーキングも重要な機会と捉える、得た知識を社内で共有し、実践につなげる計画を立てることが重要です。
外部の知識やノウハウを積極的に取り入れることで、効率的かつ効果的なHACCP導入が可能になります 。特に初めてHACCPに取り組む小規模事業者にとって、こうした支援制度や情報源の活用は大きな助けとなるでしょう。
まとめ:HACCPを形骸化させない継続的改善のポイント
HACCP導入後の運用を継続的に改善し、真に効果的な食品安全管理を実現するためのポイントをまとめます。
PDCAサイクルによる継続的改善
HACCPは一度導入して終わりではなく、継続的に改善していくことが重要です。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)による運用が効果的です。
Plan(計画)では、HACCP計画を作成・見直しします。危害要因分析に基づいた管理計画の策定、具体的な管理基準や記録方法の決定を行います。Do(実行)では、計画に基づいて実際の管理を行います。日々の衛生管理の実施、モニタリングと記録の継続を行います。Check(評価)では、管理状況を確認・検証します。記録内容の確認、定期的な内部監査や微生物検査による検証を行います。Action(改善)では、問題点を改善し計画を見直します。不適合があった場合の是正措置、検証結果に基づくHACCP計画の見直しを行います。
PDCAサイクルを継続的に回すことで、形骸化を防ぎ、常に実効性のある食品安全管理が可能になります 。特に「Check(評価)」と「Action(改善)」の部分を疎かにしないことが重要です。
従業員の意識向上と教育訓練
HACCPの効果的な運用には、現場で働く全従業員の理解と協力が不可欠です。従業員の意識向上と教育訓練のポイントがあります。
目的の共有では、なぜHACCPが必要なのか、食品安全がなぜ重要なのかを理解してもらいます。「法律だから」ではなく「お客様の健康を守るため」という本質的な目的を共有します。定期的な教育訓練では、新人教育だけでなく、定期的な再教育を実施します。衛生管理の基本から、担当工程の重要管理点の意味まで段階的に教育します。現場参加型の改善活動では、現場の従業員からの改善提案を積極的に取り入れます。小集団活動など、チームで問題解決に取り組む機会を作ります。成功事例の共有では、HACCPによって問題が未然に防げた事例を共有し、効果を実感してもらいます。良い取り組みを表彰するなど、モチベーション向上の工夫をします。
食品安全文化の構築に向けて
最終的な目標は、組織全体に「食品安全文化(Food Safety Culture)」を構築することです。これは単なる手続きやシステムを超えた、組織の価値観や行動規範として食品安全を位置づけることを意味します。
食品安全文化構築のためのポイントとして、経営層のコミットメントでは、経営者自身が食品安全の重要性を理解し、率先して取り組む姿勢を示します。必要な人材・設備・時間の投資を惜しみません。透明性の確保では、問題や失敗を隠さず、オープンに共有する文化を作ります。報告しやすい環境づくりと、報告者を責めない姿勢が重要です。継続的な学習では、常に新しい知識や技術を取り入れる姿勢を持ちます。業界の最新動向や他社の取り組みにも関心を持ちます。全員参加の意識では、食品安全は特定の部署や担当者だけの責任ではなく、全員の責任であるという意識を持ちます。部門間の壁を越えた協力体制を構築します。
HACCP義務化を単なる法令遵守として捉えるのではなく、自社の食品安全レベルを高め、消費者の信頼を獲得するためのチャンスとして活用することが大切です。HACCPを効果的に運用することで、食品事故の未然防止はもちろん、品質向上や業務効率化など、多くのメリットを享受することができるでしょう。
最終的には「記録のための記録」ではなく、真に食品の安全を確保するための仕組みとして、現場に根付いたHACCP運用を目指しましょう 。
まとめ
2021年6月からの食品衛生法改正により、原則すべての食品事業者にHACCP導入が義務化されました。HACCPは従来の抜き取り検査による事後対応型管理とは異なり、製造工程全体を継続的に監視する予防型の衛生管理システムです。科学的根拠に基づく危害要因分析により食品事故を未然に防ぎ、問題発生時の迅速な対応を可能にします。対象事業者は規模や業種により「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2区分に分けられており、小規模事業者は業界団体作成の手引書を活用した簡略化された管理が認められています。導入には7原則12手順に従った体系的なアプローチが重要であり、一般衛生管理という土台の上にHACCPシステムを構築します。IT・IoT技術の活用により記録のデジタル化や自動監視が可能となり、業務効率化と精度向上を実現できます。国や自治体の支援制度、相談窓口、講習会なども充実しており、これらを積極的に活用することで効果的な導入が可能です。重要なのは単なる法令遵守ではなく、PDCAサイクルによる継続的改善と従業員教育を通じて食品安全文化を構築し、形骸化を防ぐことです。